内科・脳神経内科について
生活習慣病とは「高血圧」「糖尿病」「脂質異常症」などの疾患を指します。これらの疾患は脳卒中を引き起こしやすく、実際に脳卒中を発症する方の多くが生活習慣病を抱えているのが特徴です。そのため、当院では生活習慣病の予防と治療に力を入れています。
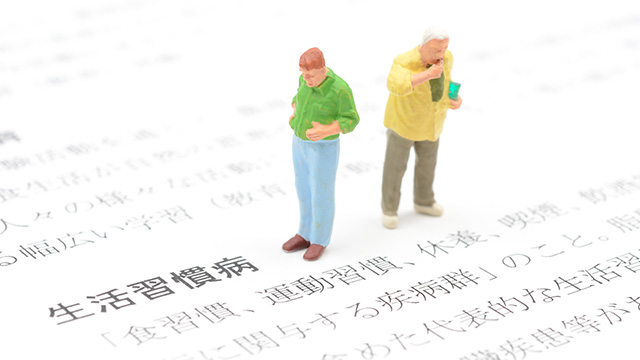
診療項目一覧
糖尿病、高血圧症、脂質異常症の生活習慣病
生活習慣病とは、かつて成人病と呼ばれ、食生活の乱れや運動不足、ストレスなどの生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている疾患の総称です。
生活習慣病には、糖尿病・高血圧症・脂質異常症などがありますが、これらは自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに進行し、脳や心臓、血管などにダメージを与えていきます。高血圧や脂質異常症などと診断されたら、たとえ症状がなくても、日々の生活を見直すことが大切です。
今までできなかった健康的な生活を継続していくことは、簡単なことではありませんが、当院では日々の経過を患者様と一緒に二人三脚で歩んでいくことを心がけます。
代表的な生活習慣病
-
糖尿病

糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)が異常に高い状態が続く病気です。食事で摂った糖分をエネルギーに変えるために必要なインスリンが十分に働かないことが原因です。インスリンは膵臓から分泌されるホルモンの一種であり、糖の代謝を調節し、血糖値を一定に保つ働きを担っています。
糖尿病には「インスリン依存型(I型)糖尿病」と「インスリン非依存型(II型)糖尿病」の2つのタイプがあります。
インスリン依存型(I型)糖尿病は、何らかの原因により、膵臓のインスリンを出す細胞が破壊されインスリンをほとんど、または全く分泌することができなくなっている状態です。糖尿病の患者様の内、全体の5%の方が、こちらのタイプです。
インスリン非依存型(II型)糖尿病は、遺伝的な影響に加えて、食べ過ぎ、運動不足、ストレスなどの環境的な影響により、インスリンが出にくくなったり、効きにくくなったりすることによって血糖値が高くなっている状態です。糖尿病の患者様の内、全体の95%の方が、こちらのタイプです。
血糖値が高い状態が長く続くと合併症を引き起こす可能性が高くなります。神経障害、網膜症、腎症、動脈硬化症など、最悪の場合は、死に至る危険な病気です。早めの治療・対策を行うことが重要です。
当院では、運動療法、食事療法、内服薬やインスリンの注射による薬物療法を行っています。膵臓の移植が必要な場合もございますので、その場合は、信頼のおける大規模な医療機関と連携して治療を行います。
-
高血圧症

高血圧は、血圧の高い状態が続く病気です。血液が血管を通る際に血管壁に与える圧力が正常より高く、慢性的に続くような状態ですが、特徴のある症状は現れません。ですが、体内では高血圧の悪影響が少しずつ広がっていきます。
高血圧には「本態性高血圧」と「二次性高血圧」の2つのタイプがあります。
本態性高血圧が、生活習慣に起因するもので、塩分の摂りすぎや運動不足、ストレスなどによって引き起こされます。
二次性高血圧は、甲状腺や副腎などの病気に起因するもので、原因となる病気が完治すれば高血圧の症状も治まります。
高血圧になると血管に常に負担がかかるため、治療せずにいると、血管が傷つき動脈硬化など重大な健康問題を引き起こしやすくなります。血管は全身に張り巡らされているので、高血圧の影響は全身にも及びます。
当院では、運動療法、食事療法、内服薬による治療を行っています。
-
脂質異常症

脂質異常症は、血液中の脂質の値が基準値から外れた状態をいいます。遺伝的な素因に加えて、高脂肪の食事や過食、運動不足といった悪い生活習慣や肥満が原因です。
脂質異常症には、3つのタイプがあります。LDL-コレステロール(悪玉コレステロール)が多いタイプ、HDL-コレステロール(善玉コレステロール)が少ないタイプ、トリグリセライド(中性脂肪)が多いタイプ。
LDL-コレステロールは、肝臓で作られたコレステロールを全身に運ぶ役割を担っている一方、過剰になると血管壁にたまって心筋梗塞や脳梗塞などの症状を引き起こす要因になります。HDL-コレステロールは、組織にたまったコレステロールを正常に保つ働きがあります。両者のバランスを保つことが大切です。
多くの場合、脂質異常症は症状が現れることはありません。ですが、体内では脂質異常症の悪影響が少しずつ広がっていきます。気がつかないうちに動脈硬化が進んでしまう恐れがあり、心筋梗塞や脳卒中を引き起こすリスクが高くなります。
当院では、運動療法、食事療法、内服薬による治療を行っています。
頭痛
日本人の3〜4人に1人が頭痛持ちと言われており、一言に「頭痛」といっても、ひとりひとりその症状も違えば、感じ方も異なります。
頭痛には、脳に異常がない機能性頭痛の「一次性頭痛」と脳に出血、腫瘍などの異常がある症候性頭痛の「二次性頭痛」があります。一次性の頭痛であれば命に関わるものではありませんが、二次性の頭痛は死に繋がる恐れがあるため、見極めが非常に大切です。自己判断はせずに当院までご相談ください。
一次性頭痛
-
緊張型頭痛

頭痛の症状を訴える方の多くが緊張性頭痛です。後頸部を中心に鈍痛を感じ、肩こりを伴うことが多いのが特徴です。精神的・身体的ストレスや筋肉の緊張などが複雑に絡み合っておこる頭痛と考えられています。特に最近はパソコン作業やスマートフォンの使用が日常生活に浸透しているため、これらが原因となり引き起こされることも多くあります。
イブプロフェンなどのNSAIDs、解熱鎮痛薬、抗炎症薬、筋弛緩薬(きんしかんやく)、抗不安薬、抗鬱薬、漢方薬の服用による治療や、ストレッチなどの運動による治療等があります。
-
片頭痛

男性よりも女性の方が症状を訴えることが多い頭痛です。頭の片側、または両側のズキンズキンとする強い痛みが特徴です。動くとがんがん響いてつらく寝込んでしまうこともあり、酷い時には、吐き気がして実際吐いてしまうなど日常生活にも影響を及ぼします。また、光や音、においに過敏になる方もいます。
片頭痛の新薬一覧 製品名
(一般名)エムガルディ
(ガルカネズマブ)アジョビ
(フレマネズマブ)アイモビーグ
(エレヌマブ)メーカー イーライリリー 大塚製薬 アムジェン 作用機序 抗CGRP抗体 抗CGRP抗体 抗CGRP受容体抗体 用法 皮下注射
1ヵ月間隔で1本
※初回2本打つ皮下注射
4週間隔で1本
または12週間隔で3本皮下注射
4週間隔で1本注射部位 腹部、大腿部、上腕部、臀部 腹部、大腿部、上腕部 腹部、大腿部、上腕部 薬価(1本) 42,675円 39,064円 38,980円 エムガルティについて
エムガルディは、片頭痛を予防するための注射薬です。片頭痛を引き起こす主な原因物質の1つに「CGRP」があります。エムガルディは、このCGRPと直接結合することにより、CGRPがCGRP受容体へ結合するのを阻害し、片頭痛の発作を起こりにくくする効果が期待できます。エムガルティを投与した患者様の中には、月10回以上の頭痛が月1〜2回に改善した方もいらっしゃいます。副作用が少なく、効果が期待できます。頭痛が多く困っている方は、お気軽にご相談下さい。
アジョビについて
アジョビも片頭痛を予防するための注射薬です。期待できる効果や作用はエムガルディと同様です。投与期間や注射部位が異なります。
アイモビーグについて
アイモビーグも片頭痛を予防するための注射薬です。CGRPではなくCGRP受容体に結合します。CGRP受容体に蓋がされ、CGRPがCGRP受容体に結合することが阻害されるので、片頭痛の発作を起こりにくくする効果が期待できます。
- ※上記3種類の予防注射の対象となる患者様
- ・過去3か月の間で、片頭痛が平均して1か月に4日以上出現している方
- ・片頭痛発作の予防薬の効果が不十分な方、または内服の継続が困難な方
-
群発頭痛

男性の20〜40歳代の方に発症することが多い頭痛です。1年から3〜4年に数回程度、1か月から数ヶ月に渡る「群発期」に毎日のように決まった時間に発症する場合が多いのが特徴です。片側の目の奥がえぐられるような強烈な痛みが起こります。
二次性頭痛
二次性頭痛は、緊急性が高く、場合により命に係わる危険性のある頭痛です。代表的なものに、くも膜下出血、脳出血、脳腫瘍などがあります。「頭痛ぐらい」と思うような自己判断はせずに当院までご相談ください。
脳神経疾患
脳卒中とは、脳の血管が詰まったり破れたりすることで、脳が損傷を受ける病気です。これらの血管の異常は、長年にわたる不健康な生活習慣によって進行することが多く、結果的に生活習慣病が原因で心臓や全身の血管が徐々に傷つき、最終的に脳の血管に影響を及ぼします。
脳卒中には、血管が詰まっておこる「脳梗塞」、血管が破れておこる「脳出血」と「くも膜下出血」の3種類があります。
3種類の脳卒中
-
脳梗塞

脳梗塞は、脳の動脈が狭くなったり詰まったりして血流が途絶え、脳細胞が死んでしまう病気です。
脳の細胞は再生がほとんど不可能で、血流が数時間途絶えるだけで深刻な後遺症や生命の危機に繋がる可能性があります。主な症状には半身麻痺、言語障害、視野の欠損などがあり、これらは障害された部位によって異なります。脳梗塞には心房細動による心原性脳塞栓症や動脈硬化によるアテローム血栓性脳梗塞などがあり、早期治療とリハビリが予後に重要な役割を果たします。
当院で行う予防・治療は、まず、健診などで脳梗塞のリスクをチェックします。血管が詰まるリスクの高い方は、血栓をつくりにくくする薬を処方いたします。また、既に動脈硬化(血管が硬く、血液が詰まりやすい状態)がある場合は、手術になる場合もあります。脳梗塞は、日本人の死因でも上位に来る恐ろしい病気ですので、発症する前に、当院にご相談ください。
-
脳出血

脳出血とは、脳内の細い血管が破れて出血し、血液が脳組織に広がる病気です。
前兆はほとんどなく、突然発症し、出血による血腫が脳細胞を破壊したり周囲の組織を圧迫して、意識障害や運動麻痺、感覚障害などの症状を引き起こします。
脳梗塞と比べて後遺症が重く、死亡率も高いです。頭痛が初期症状として現れることが多く、脳浮腫や脳ヘルニアにより命に関わる場合もあります。異変を感じたら、すぐに受診し、画像検査を受けることが望ましいと言えます。
脳出血患者の46%は高血圧の治療中、24%は未治療者から発症していたというデータがあり、血圧の管理はとても大切です。
-
くも膜下出血
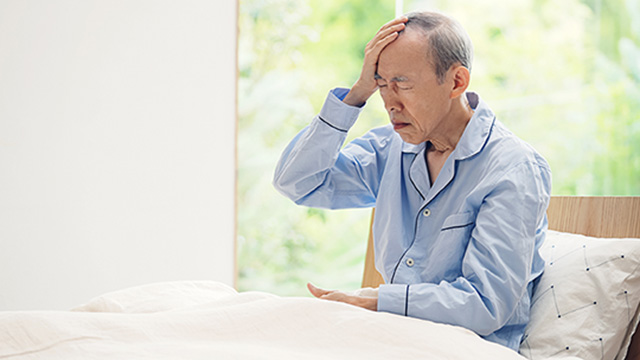
くも膜下出血は、脳を覆う硬膜・くも膜・軟膜のうち、くも膜と軟膜の間にあるくも膜下腔で出血が起こる状態です。
主な原因は脳動脈瘤の破裂で、働き盛りの人や若年者でも起こることがあり、突然発症するため「突然死」の原因としても知られています。他には脳動静脈奇形からの出血、事故や転倒などによる頭部の外傷などがあります。
前触れがないことが多いですが、動脈瘤が脳神経を圧迫すると、発症前に頭痛、めまい、吐き気、けいれん、瞼の下がりなどの症状が現れることがあります。
発症時には「今までに経験したことのない激しい頭痛」と表現されるほどの強烈な痛みを伴うのが特徴です。喫煙や高血圧、過度の飲酒はリスクを高め、家族に動脈瘤やくも膜下出血の既往がある場合は特に注意が必要です。危険因子がある方や異常を感じた場合は、早急な受診をお勧めします。

